いつもデパ地下で購入していた各地の美味しいものや、手土産に持っていっていたあのお菓子。 最近では足…
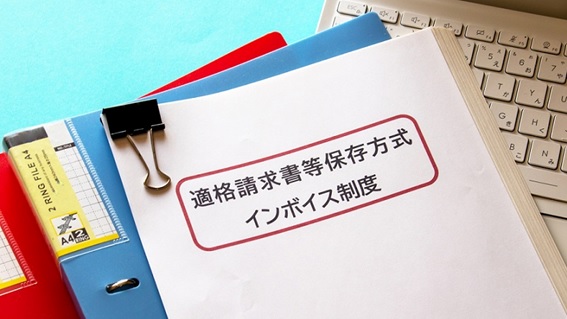
令和5年10月から始まる「インボイス制度」。その分かりにくさから「実のところなんとなくしか理解できていない…」という人は少なくありません。そこで今回は、税理士法人メディア・エス社員税理士の田中康雄氏が「インボイス制度」の基本と注意点を解説します。
「インボイス制度」ってなに?
「消費税の申告」の基本
インボイス制度により、消費税に関するルールが改正されます。そのため、消費税を申告する課税事業者への影響が特に大きいと予想されます。
まずは、インボイス制度を確認する前に「消費税の申告」の概要について、簡単に確認しておきましょう。
消費税の申告の際は、売上に係る消費税(仮受消費税)から、支払いに係る消費税(仮払消費税)を差し引いた部分を納税する仕組みになっています。仮受消費税から仮払消費税を差し引くことを、消費税の申告では「仕入税額控除」といいますが、インボイス制度では、この仕入税額控除に対して一定の制約が設けられているのです。
インボイス制度の概要
従来、消費税の申告を必要としない免税事業者が、本体価格に消費税を上乗せして請求しても、これを規制するものはありませんでした。
これは今後も変わりませんが、免税事業者にとってこうした部分が「益税」になっているとの声も多く、これがインボイス制度導入のきっかけのひとつといわれています。
(1)適格請求書への記載要件と保存義務
インボイス制度においては、請求書や領収書、レシートなどに適用税率(10%なのか8%なのか)や消費税の金額などを記載することで、消費税に関する情報を相手に正確に伝える必要があります。
また、インボイス制度では、課税事業者が消費税の申告のなかで仕入税額控除の適用を受けるため、次のような一定の情報が記載された請求書等を保存しておくことが要件とされます。
こうした消費税に関する一定の情報が記載された請求書等をインボイス制度では「適格請求書」といいますが、請求書等を発行する側も、受け取る側も、適格請求書としての記載要件をしっかりと確認しておく必要があります。
<適格請求書への記載要件>
①発行事業者の名称等と登録番号
②取引年月日と取引内容
③請求金額のうち、税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額と適用税率
④税率ごとに区分した消費税の額
⑤請求先の名称
※ なお、不特定多数の個人消費者に対して発行するレシートのようなものについては、③の適用税率や、⑤の請求先名称を省略することも認められています。
(2)「適格請求書発行事業者」について
適格請求書を発行することができるのは、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出した事業者に限られます。これらの申請書を提出すると、国税庁からは適格請求書への記載要件のひとつにもなっている「登録番号」が交付されます。そして、この登録番号が交付された事業者をインボイス制度では「適格請求書発行事業者」といいます。
このように、適格請求書発行事業者になるためには事前に申請が必要となるため、すでに課税事業者だからといって自動的に適格請求書発行事業者になるわけではありません。もっとも、課税事業者だからといって必ず適格請求書発行事業者に登録しなければならないということでもありません。
適格請求書発行事業者として登録された事業者は、その氏名や名称が登録番号とともに国税庁のホームページに公表されます。
「適格請求書発行事業者」と「免税事業者」との違い
インボイス制度では、適格請求書発行事業者から受け取った適格請求書に記載された消費税の部分しか仕入税額控除を適用することができません。つまり、適格請求書発行事業者として登録していない事業者や免税事業者への支払いについては、仕入税額控除を適用することができません(ただし、経過措置があります)。
すでに課税事業者である事業者は、支払先が仕入税額控除の適用を受けられるように、適格請求書発行事業者として登録しておくケースが多いといえます。
そのため、適格請求書発行事業者として登録した事業者は、その発行する請求書や領収書、レシートなどが適格請求書としての記載要件を満たすよう、レジや請求書等の発行システムをバージョンアップしておく必要があるといえるでしょう。
また、自身が消費税の申告をするとき、経費などの支払いに対して仕入税額控除の適用を受けるためには、支払先から受け取った適格請求書を7年間保存しておく必要があります。そのため、日常業務の見直しも検討する必要がありそうです。
ここまでのとおり、インボイス制度というのは課税事業者と課税事業者とのあいだでの消費税に関する仕入税額控除のための制度ということになります。つまり、免税事業者にとってはインボイス制度への対応はほとんど必要ないといえるでしょう。
ただし、免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出してしまうと必ず課税事業者となり、これによって消費税の申告をしなければならなくなるため、注意が必要です。
まとめ
インボイス制度は、あくまでも消費税の申告に関する改正といえます。そして、適格請求書発行事業者であっても必ずしも適格請求書を発行しなければならないということではありません。
売上先の多くが一般の個人消費者であるような業種の場合、たとえ適格請求書発行事業者の登録を済ませたとしても、適格請求書の発行への対応については、それほど急ぐ必要はないといえるかもしれません。
- 著者:
田中 康雄
税理士法人メディア・エス 社員税理士
編集:幻冬舎ゴールドオンライン
- 提供:
- © Medical LIVES / シャープファイナンス
記事紹介 more
今回は、富士通Japan株式会社よりコラムを提供いただきました。富士通Japan株式会社は、「Fuj…
『InfoBiz(MEO対策ツール)』を運営している株式会社アシスト様より、今回は特別に<シャープフ…
クリニックを開業するためには、土地や建物、または賃貸物件の探索、建築や内装工事の見積もり、医療機器や…
クリニックの開業は、自らのスタイルでしっかり患者と向き合うことができるほか、勤務形態の自由度や高額な…
クリニックの開業場所が決まり、次のステップとして考えられるのは、「オープニングスタッフの採用」と「ク…
開業医の高齢化や承継者不足を背景に、クリニックのM&Aが増加しています。買い手としては、安定して黒字…
クリニックの競争が激化している昨今、集患力を高めて経営を安定させるためには「WEBマーケティングが必…
外部環境の変化・医師の高齢化などが影響し、戦略的にM&Aを活用し、事業拡大を図る医療機関やクリニック…










